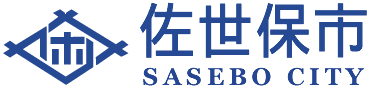ここから本文です。
更新日:2024年10月9日
【佐世保市実施】令和6年度宮中献穀事業
令和6年度は長崎県を代表して佐世保市で「宮中献穀事業」の実施が決定いたしました。
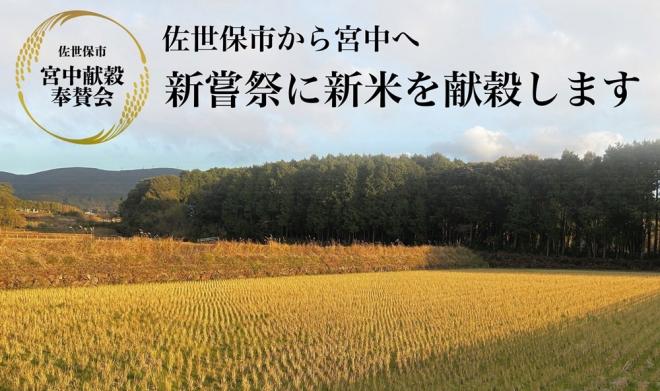
1.宮中献穀事業とは
宮中献穀事業は、明治25年から始まり、宮中行事である新嘗祭(11月23日)に、日本全国から宮中へ新米を献上する行事で、長崎県からも毎年新穀が献上されています。米生産地としてのPRをはじめ、稲作文化の継承や地元住民との交流促進など、地域の活性化を目的とした事業です。
令和6年度は佐世保市での実施が決定いたしました。佐世保市で宮中献穀事業が行われるのは、昭和57年以来42年ぶりです。(合併前の旧世知原町は平成4年に実施しています。)
【直近の県内の実施市町】
令和3年度:波佐見町、令和4年度:雲仙市、令和5年度:壱岐市
2.主な行事について
播種から田植え、収穫及び宮中献穀まで種々の行事が予定されています。
行事一覧
| 実施予定時期 | 行事名 |
| 令和6年5月 | 斎田清祓、播種祭 |
| 令和6年6月 | 御田植祭 |
| 令和6年8月 | 青田祭 |
| 令和6年10月 | 抜穂祭、献穀米清祓、宮中献穀献納式 |
| 令和6年11月 | 県知事、県神社庁への贈呈式 |
令和6年1月16日「令和6年度宮中献穀佐世保市奉賛会設立総会」
宮中献穀事業の主体となる「宮中献穀佐世保市奉賛会」が設立されました。
設立総会では、事業計画を中心に議論が進められました。

令和6年5月7日「斎田清祓」及び「播種祭」
宮中献穀事業における最初の神事となります「斎田清祓」及び「播種祭」を執り行いました。
「斎田清祓」
宮中献穀田としての斎田をお清めお祓いするとともに、土地の神様にご奉告するものです。

「播種祭」
稲の種を斎田の苗代におろすにあたって行う神聖な儀式です。

令和6年6月7日「御田植祭」
献穀田の稲作行事を始めるにあたり、五穀豊穣を祈る神事を執り行うとともに、伝統衣装をまとった早乙女に扮した柚木小学校6年生が田植えの儀式を行いました。

令和6年8月2日「青田祭」
稲を収穫するまで心配される、水不足や台風等による風水害を避け、病害虫の被害から稲を守り、豊かな実りとなるよう祈願する儀式を行いました。

令和6年10月1日「抜穂祭」
稲の収穫へ感謝する神事を執り行うとともに、伝統衣装をまとった刈男に扮した柚木小学校6年生が稲穂を刈り取る儀式を行いました。
奉耕者さまの手の行き届いた管理により、立派に育てられた献穀米が収穫できました。

今後は、収穫された稲の脱穀・籾摺り・献穀米選別を行った後、献穀米の清祓いを執り行い、10月28日に宮内庁へ献穀米を献上いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください