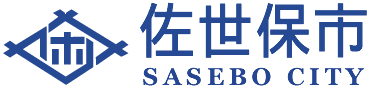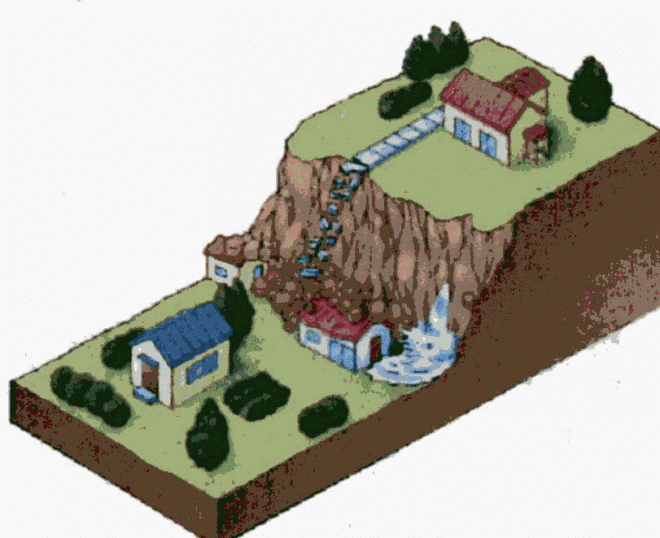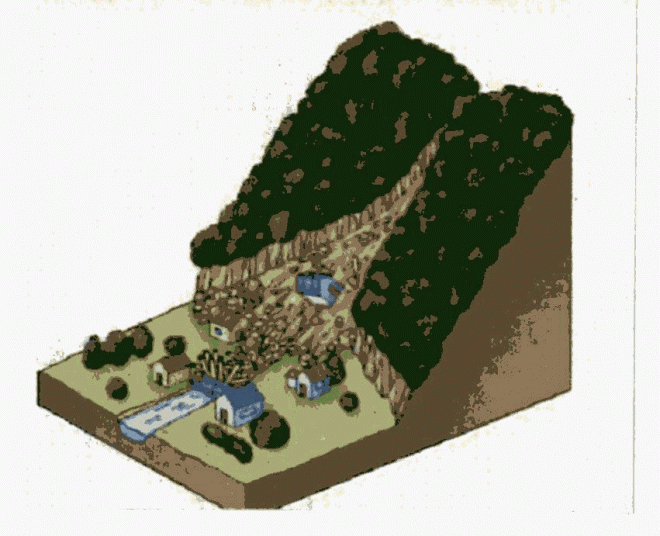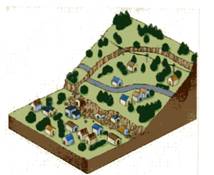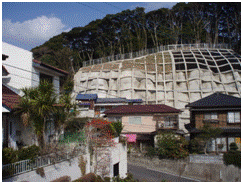ここから本文です。
更新日:2023年7月3日
土砂災害について
土砂災害には、「がけ崩れ」、「土石流」、「地すべり」の3種類があります。
|
急傾斜地崩壊(がけ崩れ) |
土石流 |
地すべり |
|---|---|---|
|
雨や地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象 |
谷間の土石が、大雨などにより水と一緒になって激しく流れ下る現象 |
雨や雪解け水が地下にしみ込み断続的に斜面が滑り出す現象 |
|
|
|
|
土砂災害は、特に梅雨や台風等による大雨や集中豪雨が原因で発生することが多く毎年のように日本各地で多くの人命や財産が奪われています。
土砂災害による被害を防ぐ、あるいは被害を最小限におさえるためには、市民ひとり一人が気象情報(テレビ・ラジオ等)や、時々刻々と変化する周囲の状況・変状に注意して自主的に早めの避難を行うことが大切です。
土砂災害(特別)警戒区域は、長崎県県北振興局砂防防災課、佐世保市土木部河川課に問い合わせることにより知ることができるほか、長崎県防災ポータルでも閲覧ができます。
日頃から自宅周辺の危険な箇所を確認し、いざという時に備えましょう。
参考
洪水危険箇所については下記の「洪水ハザードマップ」で確認ができます。
対策
佐世保市では、がけ崩れによる災害から人命を守るため、一定の採択条件を満たす「急傾斜地崩壊危険箇所」について、法枠工や擁壁工などの急傾斜地崩壊対策事業(工事)を実施しています。
|
【椎木(4)地区】
|
【名切(6)地区】
|
|
【鵜渡越地区】
|
【山手(2)地区】
|
急傾斜地崩壊対策事業の採択条件
- 斜面の勾配:30°以上
- 斜面の高さ:5m以上
- 被害の恐れのある人家:5戸以上(空き家でないこと)
- 斜面の種類:自然斜面(石積などの人工斜面でないこと)
- その他の条件
- 移転適地がないこと。
- 工事に支障となる建物の切取りは所有者が行うこと。
一定規模以上の急傾斜地崩壊危険箇所については、長崎県が国の補助を受けて急傾斜地崩壊対策事業(工事)を実施しています。
その他(「がけ地近接等危険住宅移転事業」について)
災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支援する制度です。
※「がけ地近接等危険住宅移転事業」の閲覧はこちらをクリック!
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください