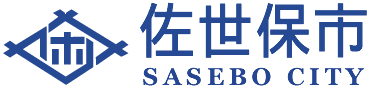ここから本文です。
更新日:2025年4月18日
年金の受給
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、年金保険料を納めた期間と免除した期間などが合わせて10年以上ある方が、原則として65歳になったときに受けとることができます。
希望により、60歳以上65歳未満の間に繰上げて請求することや、66歳以降に繰下げて請求することもできますが、この場合は受給額が増減します。
新たに老齢基礎年金対象となる方には、65歳の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から年金請求書が送られます。
【69歳以下(昭和31年4月2日以降生まれの方)】
年金額/満額:831,700円(令和7年4月~)
【70歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方】
年金額/満額:829,300円(同上)
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の納付・免除月数に応じて年金額が計算されます。
くわしくは、日本年金機構ホームページ(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)をご覧ください。
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、受給の要件を満たしているときに受けとることができます。
国民年金に加入している期間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納
付または免除されていること
(2)初診日において65歳到達日前かつ令和8年3月31日までにあり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
こと
(1級)
【69歳以下(昭和31年4月2日以降生まれの方)】
年金額:1,039,625円(令和7年4月~)
【70歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方)】
年金額:1,036,625円(同上)
(2級)
【69歳以下(昭和31年4月2日以降生まれの方)】
年金額:831,700円(令和7年4月~)
【70歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方)】
年金額:829,300円(同上)
18歳未満の子ども(障がい者の人は、20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
2人まで/各239,300円(令和7年4月~)
3人目以降/各79,800円(同上)
くわしくは、日本年金機構ホームページ(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額)をご覧ください。
遺族基礎年金
被保険者か、老齢基礎年金を受ける資格のある人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる配偶者や、子どもに支給されます。
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
【69歳以下(昭和31年4月2日以降生まれの方)】
年金額:831,700円(令和7年4月~)
【70歳以上(昭和31年4月1日以前生まれの方)】
年金額:829,300円(同上)
18歳未満の子ども(障がい者の人は20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
配偶者が受給するときには
2人まで/各239,300円(令和7年4月~)
3人目以降/各79,800円(同上)
子どもが受給するとき1人目(本人)の加算はありません。
2人目/239,300円(令和6年4月~)
3人目以降/各79,800円(同上)
くわしくは、日本年金機構ホームページ(遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額))をご覧ください。
未支給年金
年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が残っていた場合や、請求する権利があって、請求されないうちに亡くなった場合に未支給の年金が生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、これ以外の3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者等)となっています。
市では原則として障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に関する未支給年金のみの受付となりますが、国民年金(第1号及び第3号期間)のみの老齢基礎年金の場合は受付を行うことも可能です。(なお、支所窓口での受付は行っておりませんので、ご了承ください。)
短期間であっても厚生年金や共済年金の加入期間がある方は年金事務所や各共済組合でのお手続きとなります。
くわしくは、日本年金機構ホームページ(年金を受けている方が亡くなったとき)をご覧ください。
死亡一時金
第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受ける前になくなった場合に、納付月数に応じて生計を同じくしていた遺族に対し一時金が支給されます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、となっています。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料納付が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
くわしくは、日本年金機構ホームページ(死亡一時金)をご覧ください。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなられたとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます(婚姻期間が10年以上あるときに限ります)。
年金額は夫が受ける老齢基礎年金見込額の4分の3が支給されます。
くわしくは、日本年金機構ホームページ(寡婦年金)をご覧ください。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受け取ることができない人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して支給される給付金です。
くわしくは、日本年金機構ホームページ(特別障害給付金制度)をご覧ください。
問い合わせ先
≪市役所本庁舎1階≫
医療保険課年金係
TEL:0956-24-1111
≪佐世保年金事務所≫
TEL:0956-34-1189
自動音声で「1」を押し、続けて「2」を押すと、お客様相談室につながります。
住所:佐世保市稲荷町2番37号
≪ねんきんダイヤル≫(年金に関する一般的なお問い合わせ)
TEL:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話からおかけになる場合は、03-6700-1165にお電話してください。
リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください