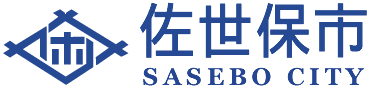ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
介護保険料Q&A
皆様からよく寄せられるご質問についてお答えします。
質問(調べたい質問をクリックしてください)
- Q1.現在63歳です。今まで介護保険料を払っていません。どうなっているのですか?
- Q2.65歳になって介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を支払っています。両方払うのでしょうか?
- Q3.65歳になったら、年金からの天引きになるのではないですか?
- Q4.介護保険料を年金天引きにする手続きはどうするのですか?
- Q5.佐世保市に転入して介護保険料の納付書が送られてきました。介護保険料は年金からの天引きで納めているのに、2重払いではないですか?
- Q6.私は無年金なのに、どうして年金をもらっている知人のほうが安いのですか?
- Q7.先日父が他界いたしました。介護保険料は年金から引かれていたようです。納めすぎの場合、戻ってくると聞いたのですが。
- Q8.今まで年金天引きだったのに、年金から引けなくなったと納付書が送られてきました。どうしてですか。
- Q9.夫婦でそれぞれの年金額に差があるのに、同じ金額の介護保険料なのはなぜですか?介護保険料は年金の額に応じて決まるのではないのですか?
- Q10.夫の私が課税になると、どうして所得の無い妻の介護保険料が上がるのでしょうか?
- Q11.介護保険料も国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と同じように年金天引きから口座振替に変更できるのでしょうか?
答え
Q1.現在63歳です。今まで介護保険料を払っていません。どうなっているのですか?
A1.40歳から64歳の方(第2号被保険者)であれば、加入している健康保険の保険料と併せて介護保険料を納めています。ただし、社会保険などの健康保険に扶養で入っている人は、勤めている人が保険料を負担しますので、ご自身で支払うことはありません。金額については健康保険ごとに異なりますので、ご加入の健康保険にお尋ねください。
国民健康保険の方は、関連情報をご参照ください。
Q2.65歳になって介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を支払っています。両方払うのでしょうか?
A2.65歳になった月分からは、健康保険での介護保険料負担はなくなります。今後は、届いた納付書でお支払いください。
健康保険の介護保険料については、ご加入の健康保険にお尋ねください。
※国民健康保険に加入している方の場合は、年度途中に65歳になられることを見越して、あらかじめ介護分を差し引いた額で納めていただいています。
Q3.65歳になったら、年金からの天引きになるのではないですか?
A3.年金受給者は年金天引き(特別徴収)が原則ですが、特別徴収が始まるまでには、少なくとも6ヶ月以上の日数を要します。したがって、それまでは納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
Q4.介護保険料を年金天引き(特別徴収)にする手続きはどうするのですか?
A4.手続きの必要はありません。年金天引き(特別徴収)は、徴収可能になれば自動的に開始されます。それまでは納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
また、年金天引きを止めて普通徴収にする手続きもありません。
Q5.佐世保市に転入して介護保険料の納付書が送られてきました。介護保険料は年金からの天引きで納めているのに、2重払いではないですか?
A5.年金から天引きされている介護保険料は、前の住所地の保険料になります。いずれ天引きは停止され、納めすぎであれば前住所地から連絡があります。
今後は、佐世保市に介護保険料を納めなければなりませんが、すぐに年金から徴収することはできません。したがって、年金からの徴収が開始されるまでの間、納付書や口座振替(普通徴収)で納めることになります。
Q6.私は無年金なのに、どうして年金をもらっている知人のほうが安いのですか?知人の介護保険料は年金からの天引きで2ヶ月ごとに5,600円(月あたり2,800円)、私は毎月納付書で3,300円支払っています。
A6.介護保険料は年度ごとに13段階に分けて金額が決まります(下記関連情報参照)。
ですから比較をするときはそれぞれ何段階なのかを比べなければなりません。年金からの天引き(特別徴収)であれば、10月の年金から天引き額が変わるため、年度の前半と後半で徴収額が違います。また、納付書や口座振替(普通徴収)で支払う方であれば、何回に分けて納めているかによって、1期あたりの徴収額が違ってきます。段階や期ごとの徴収額は通知書に記載してありますので、そちらをご確認ください。
Q7.先日父が他界いたしました。介護保険料は年金から引かれていたようです。納めすぎの場合、戻ってくると聞いたのですが?
A7.ご本人様がお亡くなりになったために、年金から特別徴収された介護保険料に余分が生じた場合は、その余分になった金額を日本年金機構などの年金支払者に戻す場合と、ご遺族様にお返しする場合があります。もしご遺族様にお返しする場合は、市役所からご連絡いたします。ただし、どちらへ返すべきか判明するまで数ヶ月を要しますのでご了承ください。
また、年金保険者への死亡届など、すみやかに行っていただきますようお願いします。
Q8.今まで年金天引きだったのに、年金から引けなくなったと納付書が送られてきました。どうしてですか。
A8.年金からの天引きが停止になるのには、年金保険者(厚生労働大臣や共済組合など)が中止する場合と、市町村が中止を依頼する場合があります。
年金保険者が介護保険料の天引きを中止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届の提出忘れなどの手続漏れもその原因になります。
市町村が中止を依頼するのは、年度途中で介護保険料の段階が下がった場合や、その人が市町村の住民でなくなった場合(転出・死亡)などです。
Q9.夫婦共働きでしたので、それぞれ厚生年金をもらっています。ただ受け取っている年金額には差があります。それなのに、同じ金額の介護保険料を引かれているのはなぜでしょうか?夫の年金は220万円、妻の年金は160万円です。2人とも65歳以上で年金以外の収入はありません。子供は独立していて扶養者はおりません。
A9.現行では、介護保険料は13段階に分けて決められています。年金額に比例して払う仕組みではありません。
年金220万円は、合計所得にして110万円、年金160万円は50万円に相当します。
扶養者がおられないということですので、お2人とも市民税が課税になられます。
市民税が課税で合計所得が120万円未満であれば、第6段階に区分されますので、お2人とも同じ保険料になります。
Q10.夫の私が課税になると、どうして妻の介護保険料が上がるのでしょうか?
昨年度、介護保険料は夫婦とも第3段階でした。ところが今年度は、夫の私に市民税が課税され、私が第6段階、妻が第5段階になっています。
私はともかく、どうして妻の段階が上がるのでしょう。妻は収入が変わってないのに、夫婦ともに増額されるのは負担が大きく納得できません。
A10.第4段階と第5段階とは、当人の収入や所得に関係なく、世帯に市町村民税の課税者がいるかいないかで分けられています。設問の場合、夫が課税なので、同一世帯の市町村民税非課税の妻は第5段階になります。妻の収入が増えた訳では無いですから、夫一人の収入で家計を支えている世帯の負担感が大きいですが、現行の制度では止むを得ないところです。
Q11.国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、年金天引きから口座振替へ変更ができると聞きました。介護保険料も口座振替へ変更できるのでしょうか?
A11.介護保険料については、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料とは異なり、納付方法変更の申出の制度はありませんので、申出による年金天引きから口座振替への変更はできません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください