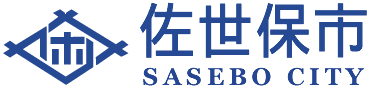ここから本文です。
更新日:2025年5月29日
後期高齢者医療保険料Q&A
- (Q1)保険料は、誰が納めるのですか?
- (Q2)保険料は、いくらになるのでしょうか?
- (Q3)収入が少ない世帯に対して、保険料が安くなる制度はありますか?
- (Q4)保険料の一人当たりの最低額と最高額を教えてください。
- (Q5)保険料を納める方法を教えてください。
- (Q6)保険料はいつから納めるのですか?
- (Q7)私は先月75歳になりました。後期高齢者医療保険料は、介護保険と同じように年金から天引きされるものと思っていましたが、7月に「後期高齢者医療保険料」の納付書が送られてきました。どうしてですか?
- (Q8)子(世帯主)の世帯に同居しています。私の年金は年間50万程度で少ないものですが、保険料の軽減措置が受けられないとのことでした。どうしてですか?
- (Q9)もうすぐ75歳になります。現在、子供の社会保険の被扶養者になっています。今まで保険料は支払っていなかったのですが、後期高齢者医療保険になるとどうなるのでしょうか?
- (Q10)夫婦二人で生活しています。世帯主の夫が、後期高齢者医療保険で、私(妻)が国民健康保険です。夫は、4月の年金から保険料を引かれているのですが、6月に国保税の納付書が夫宛に送られてきました。二重に納めているのではないですか?
- (Q11)もうすぐ75歳になります。現在、社会保険に加入しており、今後も継続して働く予定です。医療保険はどうなるのでしょうか?
- (Q12)保険料を年金から天引きされています。天引きしないようにできますか?
(Q1)保険料は、誰が納めるのですか?
(A1)加入者本人に納めていただくことになります。
後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入者本人に保険料が賦課され、納めていただくことになります。
(Q2)保険料は、いくらになるのでしょうか?
(A2)加入者等の収入状況により、保険料が異なります。
加入者等の収入によって決定しますので、一定の額ではありません。
計算は、加入者みなさんに均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」を足したものが、年間保険料となります。
後期高齢者医療保険料(年間分)の計算方法
|
均等割 |
所得割 |
賦課限度額(年額) |
|---|---|---|
|
52,400円 |
(課税所得金額注1の) 10.31% |
800,000円 |
注1…課税所得金額とは、総所得金額等から基礎控除(原則43万円)を差し引いた額です。総所得金額等とは、「年金収入ー公的年金等控除」、「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」等で、各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
(Q3)収入が少ない世帯に対して、保険料が安くなる制度はありますか?
(A3)収入が少ない(または、収入がない)方については、次のとおり保険料の軽減措置がとられます。
加入者と世帯主の所得水準に応じて保険料の軽減措置が設けられています。
均等割部分
|
軽減割合 |
被保険者及び世帯主の所得を合計した |
|---|---|
|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数注1ー1)以下の場合 |
|
5割 |
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
|
2割 |
43万円+(56万円×被保険者数)+10万×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 |
注1…給与所得者等の数とは以下の1、2のいずれかの要件を満たす方の合計人数です。
1.給与収入で55万円を超える方
2.公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または125万円を超える65歳以上の方
その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で軽減判定を行います。(所得が15万円に満たない場合は、その額を差し引きます。)
軽減判定の際には、世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者で無い場合でも、対象に含めます。
|
被用者保険の被扶養者だった方は被保険者になってから 2年を経過する月までの間(所得、世帯状況は関係なし) |
5割 |
|---|
(Q4)保険料の一人当たりの最低額と最高額を教えてください。
(A4)最低額15,700円【年額】(均等割(7割軽減)15,700円+所得割0円)
最高額800,000円【年額】(均等割52,400円+※所得割747,600円以上)
(注)最高額の保険料うち、所得割額が747,600円を超過する場合がありますが、その場合については、747,600円が上限の金額となります。
後期高齢者医療保険は、加入者本人に保険料が発生します。夫婦ともに後期高齢者医療保険に加入された場合は、それぞれ保険料が発生し納めていただくことになります。
(Q5)保険料を納める方法を教えてください。
(A5)納付の方法は、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の二つに分かれます。
|
特別徴収 |
年金天引きのことです。以下の条件をすべて満たす方は特別徴収となります。
|
|---|---|
|
普通徴収 |
納付書、口座振替でのお支払いのことです。 特別徴収の条件を満たさない方は普通徴収となります。 |
(Q6)保険料はいつから納めるのですか?
(A6)徴収方法により、納める開始時期が異なります。
特別徴収
原則4月からです。毎年、10月に保険料が変更されます。
(例外もあります。詳しくはQ7へ。)
2ヶ月に一度の年金支給の際に差し引きます。
| 4月 |
仮徴収 |
仮徴収額(4月、6月、8月の徴収額)は、前年度の保険料をもとに決定され、前年度に特別徴収されている方の場合は、前年度2月と同額ずつ徴収されます。 |
|---|---|---|
| 6月 | ||
| 8月 | ||
| 10月 |
本徴収 |
本徴収額(10月、12月、2月の徴収額)は、当年度の保険料の年額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ徴収されます。(端数は10月に上乗せ) |
| 12月 | ||
| 2月 |
本徴収額とのバランスをとる目的で、6月、8月の徴収額を変更することがあります。
普通徴収
後期高齢者医療保険料は、7月~3月までの9期に分けて支払います。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
支払方法は個人の状況によって違います。
特別徴収と普通徴収を合わせた支払方法になる場合があります。
(Q7)私は先月75歳になりました。後期高齢者医療保険料は、介護保険と同じように年金から天引きされるものと思っていましたが、7月に「後期高齢者医療保険料」の納付書が送られてきました。どうしてですか?
(A7)後期高齢者医療制度に移行してしばらくは、みなさん普通徴収(納付書・口座振替)です。
特別徴収の準備が整い次第、順次特別徴収となっていきます。
|
75歳の誕生日 |
特別徴収の開始時期 (めやす) |
|---|---|
|
2月3日~4月2日 |
翌年度の10月 |
|
4月3日~10月2日 |
翌年度の4月 |
|
10月3日~12月2日 |
翌年度の6月 |
|
12月3日~2月2日 |
翌年度の8月 |
特別徴収になるには、一定の要件が設けられています。以下の要件に該当される方は、特別徴収となりません。
- 年間受給額が18万円未満の方
- 受給額が年間18万円以上であっても、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、受給額の2分の1を超える方
年度途中で前年中の所得に変動があった場合(修正申告をされるなど)、「年金天引き」から「納付書」での納付へ変更となる方や「天引き」と同時に「納付書」での納付をお願いする場合があります。
二つ以上の年金を受給されている方は、介護保険料を特別徴収されている年金が年額18万円以上でなければなりません。受給している年金の合計額ではありませんのでご注意ください。
(Q8)子(世帯主)の世帯に同居しています。私の年金は年間50万程度で少ないものですが、保険料の軽減措置が受けられないとのことでした。どうしてですか?
(A8)軽減判定は、加入者と世帯主の所得の合計額で判断されます。
世帯主が後期高齢者医療制度の加入者でない場合であっても、保険料の軽減判定に含まれます。(保険料の計算には含まれません)
また、加入者及び世帯主が収入申告を行っていない場合は、例え収入が無かった場合でも軽減措置を受けることはできません。必ず申告が必要になります。
(Q9)もうすぐ75歳になります。現在、子供の社会保険の被扶養者になっています。今まで保険料は支払っていなかったのですが、後期高齢者医療保険になるとどうなるのでしょうか?
(A9)75歳以上の方は、現在の医療保険を脱退され後期高齢者医療制度へ加入することになります。
保険料についてですが、加入者本人が保険料を負担することになります。
ただし、加入の前日まで社会保険の被扶養者であった場合、所得割額はかかりません。また、被保険者になって2年を経過する月までの間は均等割額を5割軽減します。よって、年間額は26,200円になります。
軽減を受けるための手続きは不要です。社会保険から直接情報が届くためです。
社会保険からの情報の到着時期によって、軽減適用時期が遅れる場合があります。
(Q10)夫婦二人で生活しています。世帯主の夫が、後期高齢者医療保険で、私(妻)が国民健康保険です。夫は、4月の年金から保険料を引かれているのですが、6月に国保税の納付書が夫宛に送られてきました。二重に納めているのではないですか?
(A10)重複納付ではありません。
国保税は、妻の分になります。
4月の年金から天引きされている保険料は、「後期高齢者医療保険料」です。6月に送付された納付書は、「国民健康保険税」です。
後期高齢者医療保険料は、加入者本人に賦課され納付義務が発生しますが、国民健康保険税は、「世帯単位」で課税されますので、世帯主宛に納付書を送付させていただくことになります。
6月に届きました国保税の内訳は、妻のみの税額となっています。
(Q11)もうすぐ75歳になります。現在、社会保険に加入しており、今後も継続して働く予定です。医療保険はどうなるのでしょうか?
(A11)後期高齢者医療制度に加入・保険料の納付が必要になります。
後期高齢者医療制度は、すべての75歳以上(一定の障がいがある65歳以上の方で、長崎県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含みます)の方に加入していただくものです。
保険料については、被用者保険を脱退することになりますので、被用者保険の保険料を納める必要はなく、新規に加入される「後期高齢者医療保険料」を納めていただくことになります。
(Q12)保険料を年金から天引きされています。天引きしないようにできますか?
(A12)手続きしていただくことによって、口座振替へは変更できます(納付書への変更はできません)。
詳しくは、後期高齢者医療保険料の特別徴収から普通徴収への変更についてをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください