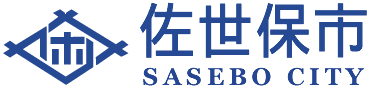ここから本文です。
更新日:2025年11月27日
【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年10月31日をもって申請受付を終了しました。
期限後の申請はお受けできませんのでご了承ください。
|
給付金を装った詐欺にご注意ください! 本給付金に関して、佐世保市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。不審な電話やメール、訪問等にはくれぐれもご注意ください。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください