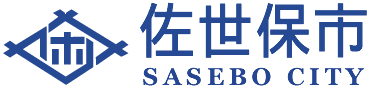ホーム > 市政情報 > 計画 > 特定複合観光施設(IR)誘致の取組について > 【広報させぼ・2021年12月号】産学民関係者インタビュー:産業界(紙面:8・9ページ)
ここから本文です。
更新日:2021年11月22日
【広報させぼ・2021年12月号】産学民関係者インタビュー:産業界(紙面:8・9ページ)
産業界:基地と共にIRを「地域経済活性化のエンジン」に

佐世保商工会議所(九州IR推進協議会理事)
会頭金子卓也さん
〇佐世保にIRができることを商工会議所としてどのようにお考えですか。
明治22(1889)年の佐世保鎮守府開庁を機に、佐世保は基地経済を中心に「基地のまち」として発展を遂げてきました。
鎮守府設置後、国の要衝となった佐世保には全国から多くの人が移り住み、急速に人口が増加し、明治35(1902)年には町制を飛び超え、村から一気に市へと成長しました。
現在も東アジアの安全保障の要として佐世保には米海軍基地や海上自衛隊、陸上自衛隊水陸機動団があり、基地と地域経済は深い関わりを持っています。
商工会議所では、基地があることを佐世保の特性と捉え、佐世保の経済発展と豊かで住み良い街づくりのために、さまざまな活動を行っています。
私は、地方都市の中でも佐世保は「キラっと輝く可能性」を持っていると思います。
佐世保は人口25万人ほどのコンパクトなまちですが、県北地域や有田・伊万里などを含めると40万人近い広域の経済圏を有しています。
また、福岡や長崎など近隣都市とも適度に距離が離れ、競合することなく一つの独立したまちとして成り立っており、さらには基地との共存共生によって生まれた経済エネルギーも持っています。
こうした佐世保が持つポテンシャルにIRが加われば、いろいろな相乗効果が生まれると思いますし、IRは基地とともに「地域経済活性化のエンジン」となることを期待しています。
〇IRにどのようなことを期待しますか。
IRは地方活性化につながる大きな可能性を秘めています。
例えば、ラスベガスではIRは健全なレクリエーションの場であり、エンターテインメントのまちとして成功しています。
また、世界レベルのショーやエンターテインメント、見本市などが行われており、「九州・長崎IR」でも世界中から多くの人が訪れるまちを目指していきたいと考えています。
今の佐世保には「郷土愛」や核となるような「佐世保らしさ」が不足しているように感じます。
まちの求心力を何に持たせるかは都市によってさまざまですが、さらなる輝きを手にするためには文化や伝統を生かした核づくりが必要であり、IRがそのきっかけになると考えています。
今回、IRの設置運営事業者がオーストリア共和国の国有企業グループである「CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL JAPAN(カジノオーストリアインターナショナルジャパン)」に決定しました。
長い歴史の中でも長崎県はヨーロッパとの関わりが深く、舞台となるハウステンボスもオランダの街並みを再現してつくられています。
今回IRのコンセプトの一つに「東洋と西洋文化の調和」が掲げられており、幅広い分野で集客力の高い魅力的で最先端のコンテンツの提供を提案されています。
ヨーロッパの有名合唱団や楽団などを招へいできれば、佐世保に大きなにぎわいが生まれますし、子どもたちも身近に世界一流の文化を体験できるようになります。
そうした点でもIRには「基地のまち」と同じくらいの将来性を感じますし、佐世保が「東アジアの中のヨーロッパの発信地」となれば、佐世保のさらなる発展が期待できます。
〇CAIJは「地元調達100%」を掲げられていますが、商工会議所としてどのように受け止められていますか。
経済面でもCAIJは地方創生や地域経済への貢献として「地元調達100%」が掲げられており、私たちも大きな期待を寄せています。
IRでは年間約840万人(1日約2~3万人)もの来訪者が見込まれており、安定した供給を継続して行うためには多くの関連企業の力が必要であり、佐世保に限らず長崎や九州全体を含めた「オール九州」での支援態勢が必要です。
佐世保が旧海軍鎮守府の設置によって発展を遂げてきたように、IR誘致によって全国から人が集まり定着すれば、まちの底上げにもつながります。
佐世保は多様性を受け入れる風土がありますので、関連企業の皆さまには営業所などを地域に構えていただき、地域に根付いた企業となれるように私たちも行政と連携しながら支援をしていきます。
IRは百年に一度のビックチャンスであり、IRが誘致できれば「第二の開港」とも言える大きなインパクトを世界に与えられると思います。
これから交通インフラや周遊型観光の促進など、IR誘致に向けた環境整備が進められていきます。IR誘致を好機と捉え、将来のまちづくりの礎を築くために、これからも全力を注いで貢献していきたいと思います。

【九州IR推進協議会(KIRC)】(KIRC発足式での共同宣言の様子)
九州経済界、議会、行政で構成される協議会。本年4月12日には九州へのIR誘致、IR需要の地元調達確保、九州全域の魅力発信を実行する共同宣言が行われました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください