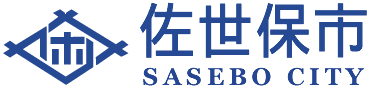ホーム > 健康・福祉 > 健康 > させぼ★みんなの食育ひろば > 食育とは > 基本目標10食文化(伝統的な料理や作法など)を継承し、伝えている市民を増やす
ここから本文です。
更新日:2024年12月3日
基本目標10食文化(伝統的な料理や作法など)を継承し、伝えている市民を増やす
食文化の継承について
令和2年度に実施した、佐世保市食育に関するアンケート調査の結果によると、食文化の継承について、小児において正しい箸の持ち方を実践している人の割合は未就学児、小学2年生、小学5年生で約70%、中学2年生で約80%でした。
また、16歳~79歳において、「郷土料理などに関心を持つこと」に取り組んでいると回答した人の割合は43.7%でした。
食育の取り組みについて「今後取り組みたい」と回答した人に取り組みたい内容を尋ねたところ、「郷土料理などに関心を持つこと」について45.4%で、3番目に高い割合でした。
|
【推進項目】 |
現状値 令和2年度 |
目標値 令和8年度 |
|---|---|---|
|
正しい箸の持ち方ができる子どもの割合 |
(小学2年生)68.4% (小学5年生)71.8% (中学2年生)82.4% |
75.0% 80.0% 90.0% |
| 郷土料理などに関心を持つ市民の割合 | 43.7% | 50.0% |
毎年11月24日は”いい・にほん・しょく”の日で「和食の日」
日本和食文化国民会議では、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された「和食・日本人の伝統的な食文化」を次世代へと保護・継承していくことの大切さを改めて考える日として、11月24日を「和食の日」と制定されています。
和食の基本は”一汁三菜”
日本人の主食である「ごはん」、みそ汁などの「汁物」、3つの「おかず(菜)」を組み合わせた献立です。
体に必要な「エネルギーになる炭水化物」「体をつくるたんぱく質」「体の調子を整えるビタミンやミネラル、食物繊維」などの栄養素をバランスよく摂ることができます。
三菜の組み合わせ方はさまざま
必ずしも汁物以外のおかずが3つないといけないというわけではありません。
1食の食事全体でまんべんなく栄養が摂れることが大切です。
忙しい暮らしの中で、おかずを3つも用意するのは難しいでしょう…。
そんな時は以下の方法でバランスをとることができます。
1.全部を手作りせず、封を切るだけ・お皿に出すだけのおかずを用意する。
(冷ややっこ・納豆、ミニトマトなど)
2.市販のサラダやお惣菜、缶詰などを利用して、手間を省く。
3.多めに作り置きして、数日にわけて食べる。
今より少し頑張ってみる
1日3食すべてで”一汁三菜”をそろえるのは大変ですので、「3食のうち1食」「1週間のうち3日」など、今の食事より意識してバランスをとることから始めてみましょう。
お箸を正しく持ちましょう!
食事のときに、正しい姿勢で、正しくお箸を持つことで、家族や周囲の人々と気持ちよく食事をすることにつながります。
食事のときの正しい姿勢
1.背筋をのばしましょう。
2.足の裏をきちんと床につけましょう。(イスが高いときは足元に台を置くなどして調整します)
3.テーブルにひじをつかないよう注意しましょう。
4.お箸を持っていない方の手はお皿を持ったり、添えたりするなどしましょう。(片手で食べない)
食事のときの正しいお箸の持ち方
1.持つ場所は、箸先から約3分の2のところです。
2.上の箸はえんぴつと同じように持ちます。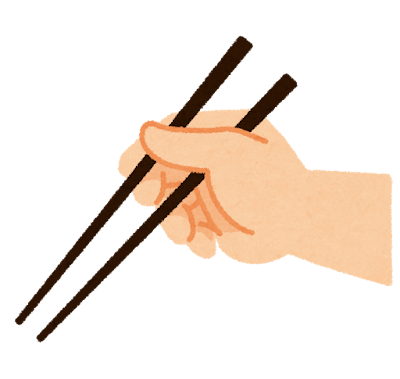
3.下の箸は中指と薬指の間に入れて固定します。
4.物をつまむときは、中指と人差し指と親指で上の箸を動かし、下の箸は動かしません。
箸先を開いたり、すぼめたりすることで、大きなものも小さなものも自由自在につまめます。
伝えていますか?感謝の気持ち
食事の前、食べ終わった後のあいさつの意味を知って、
食事に関わるすべての人や命に感謝しましょう。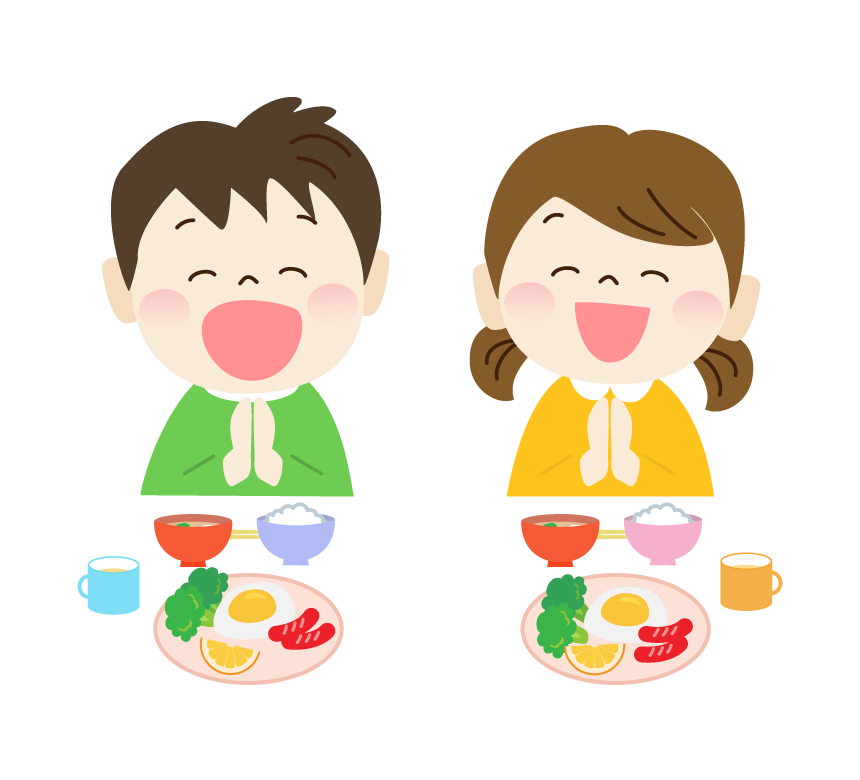
食事の前の「いただきます」
「いただく」は、もともと「頭にのせる」の意味ですが、物をもらう、食べるの謙譲語として使用されるようになりました。
自然の恩恵、お米や農作物を作ってくれた農家さん、お魚を獲ってくれた漁師さん、食材を運んでくれた運送業者さん、そして食事を準備してくれた人への感謝など、さまざまな感謝の気持ちが込められています。
食べ終わった後の「ごちそうさまでした」
漢字で書くと「ご馳走(ちそう)さまでした」と書きます。
「馳走」とは、食事の用意で走り回ることです。
今のように近所にスーパーがない、車もない時代の食事作りは、食材を手に入れるために遠くまで走り回らなくてはなりませんでした。
すぐに食材を手に入れることができるようになった現代ですが、食べる人のことを思い、食事を作る
ということは変わりません。
毎日の食事を当たり前と思わず、感謝の気持ちをもって、美味しくいただきましょう。
ライフステージ別の取り組み
食文化の継承のためのライフステージ別の取り組み内容を確認し、実践につなげましょう!
乳幼児期(0~5歳頃)
箸を使って食べましょう。
郷土料理や伝統料理にたくさん触れさせてあげましょう。
学齢期(小中学生)
正しい箸の持ち方を身につけましょう。
郷土料理や伝統料理を理解しましょう。
青年期(16歳から29歳)
郷土料理や伝統料理を作ってみましょう。
壮年期(30歳から64歳)、高齢期(65歳以上)
生活の中に郷土料理や伝統料理を取り入れながら次世代に伝えましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください