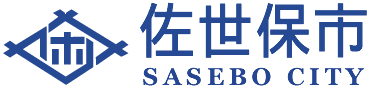ここから本文です。
更新日:2025年5月29日
国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度
前年中の所得が一定の基準額より低い世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
対象となる世帯
世帯主と世帯主以外の加入者(被保険者)の前年中の所得が、世帯の加入者数に応じた軽減判定基準額以下の世帯です。
軽減の割合
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と世帯割額(平等割額)を各割合で軽減します。国保税額は、軽減した後の金額でお知らせします。
軽減の適用について
軽減判定の対象となる「世帯の所得金額」が、世帯の「軽減判定基準額」以下となることが必要です。「軽減判定基準額」は、世帯内の加入者数と給与所得者等数によって異なります。
「世帯の所得金額」が、2割軽減の「軽減判定基準額」を超える場合は、軽減適用なしとなります。
軽減判定の対象となる「世帯の所得金額」
軽減判定の対象となる「世帯の所得金額」とは、世帯主の前年中の所得と、世帯主以外の加入者(次の(注)の方を含む)の前年中の所得との合計額です。
(注)加入者が75歳になるなどして後期高齢者医療制度へ移行した場合、世帯に異動がない限り、後期高齢医療保険へ移行した方も加入者に含めて軽減判定をします。
- 世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入している場合であっても、世帯主の所得を含めて「世帯の所得金額」を計算します。
- 世帯主または世帯内の加入者に所得がマイナスの方がいても、他の世帯員との損益通算はできません。(マイナスの方は所得0円として計算します。)
- その年の1月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。所得が15万円に満たない場合はその全額を差し引きます。
- 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
- 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(軽減判定においては、専従者本人の給与とは扱いません。)
収入の申告について(収入がない場合も申告が必要です)
- 軽減の対象となるにあたっては、世帯主及び世帯内の加入者全員について、原則として収入の申告が必要です。
- ただし、給与収入(会社等から給与支払報告書が市役所に提出されている給与に限る)や公的年金等収入のみで、所得税の確定申告または市県民税の申告が不要となる方、ならびに、収入がある場合で所得税の確定申告または市県民税・国保税等の申告を済ませた方は、収入の申告は不要です。
- 控除対象配偶者や扶養控除の対象者ではなく、かつ、収入がない方については、「市県民税・国保税等の申告書」により、収入がない旨の申告を行うことが必要です。
加入者数
年度初めである、4月1日の世帯内の加入者の人数(前記(注)の方を含む)を用います。ただし、年度途中で新規加入した世帯は、国保加入の日の加入者数を用います。
4月1日付で社会保険に加入された方がいる場合は、国保資格の喪失が4月2日付となることから、その方の人数や前年所得を含めて判定することになりますのでご注意ください。
軽減は該当年度を単位に適用されます。年度中に加入人数の増減があっても、軽減額を月割したり、軽減判定を再度行うことはありません。(年度初めの4月1日の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
給与所得者等数
給与所得者等数とは、次のいずれかの要件を満たす方の合計人数をいいます。ただし、下記2つの両方を満たす場合は、1人として数えます。年齢は、令和7年1月1日現在の年齢で判断します。
- 給与収入で55万円を超える方
- 公的年金等収入が60万円を超える65歳未満の方、または125万円を超える65歳以上の方
「軽減判定基準額」の求め方(令和7年度)
令和7年度の「軽減判定基準額」の求め方は、次のとおりです。
| 軽減判定基準額 | |
|---|---|
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
| 5割軽減 | 43万円+(30万5千円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
| 7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
「(10万円×(給与所得者等数-1))」の金額については、1人まで「0円」になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください