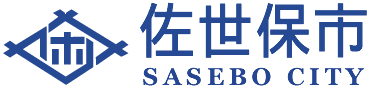ここから本文です。
更新日:2025年5月29日
国民健康保険税額の算定
佐世保市では、国民健康保険にかかる保険料を、地方税法の規定による国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)として賦課しています。
算定のための基本事項
- 世帯ごとに計算します。(一世帯分を世帯主の名前でまとめて納めることになります。)
- 年度(4月から翌年3月)単位で計算します。
- 佐世保市の国保税額を算定する要素は、所得割、均等割、世帯割の3つがあります。
- 医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の方のみ)をそれぞれ計算し、その合計額が国保税額になります。
- 所得割の計算については、課税すべき年度(4月から翌年3月)の前の年(1月から12月)の所得を用います。(所得の計算方法については「所得の種類と計算方法」のページをご覧ください。)
令和7年度の税率(年額)(注)税率は年度ごとに見直されます
|
|
医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 (40歳から64歳までの方のみ) |
説明 |
|---|---|---|---|---|
|
所得割 |
8.0% |
3.4% |
2.8% |
加入者の前年中の所得に応じて加算される額です。所得から基礎控除額43万円(原則)を引いて、左記の所得割率を掛けます。令和7年度は令和6年の1月から12月の所得を使います。 |
|
均等割 |
24,600円 (注1) |
10,600円 (注1) |
10,600円 |
加入者一人につき加算される額です。 |
|
世帯割 |
18,000円(注2) |
7,300円 (注2) |
5,000円 |
一世帯ごとにかかる基本額です。 |
|
課税限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
最高額は109万円(介護分のかからない世帯は92万円)です。一世帯につきこれ以上は課税されません。 |
(注1)未就学児に係る均等割額の軽減制度について
子育て世帯の経済的負担軽減の拡充として、平成31年4月2日以降生まれの未就学児の方は、均等割額が半額になります。均等割・世帯割が軽減対象の世帯の方については、軽減後の均等割額から半額になります。
(注2)特定世帯に対する減額について
「特定世帯」は、医療分と後期高齢者支援分の世帯割が5年が経過する年の年度末まで、半額になります。さらに「特定継続世帯」は、引き続き3年が経過する年の年度末まで、4分の1の額が減額になります。
特定世帯及び特定継続世帯とは・・・世帯内の国民健康保険加入者が(75歳になるなどして)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数が1人になった世帯をいいます。
均等割・世帯割の軽減制度
前年中の所得が一定の基準以下の世帯を対象に、均等割額と世帯割額を減額する制度です。くわしくは、「国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度」のページをご覧ください。
保険税の計算例
例として、次の3人世帯の税額を計算します。
| 構成 | 年齢 | 令和6年中の所得 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
| 世帯主 | 45歳 | 給与所得95万円(給与収入150万円) | 該当 | 該当 | 該当 |
| 妻 | 43歳 | 収入なし(所得なし) | 該当 | 該当 | 該当 |
| 子 | 22歳 | 給与所得50万円(給与収入105万円) | 該当 | 該当 | 非該当 |
均等割・世帯割の軽減判定
軽減判定用の「世帯の所得金額」を計算し、「世帯の軽減判定基準額」と比較して、軽減割合を求めます。
なお、軽減判定用の「世帯の所得金額」は、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入している場合であっても、世帯主の所得を含めて計算します。
- 「世帯の所得金額」は、95万円+50万円=145万円となります。
- 「世帯の軽減判定基準額」の計算結果は、下表のとおりとなります。
- 「世帯の所得金額」と「世帯の軽減判定基準額」を比較すると、221万円≧145万円>144万5千円となるため、2割軽減世帯に該当することになります。
| 軽減判定基準額 | |
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×3人)+(10万円×(2人-1))=221万円(以下) |
| 5割軽減 | 43万円+(30万5千円×3人)+(10万円×(2人-1))=144万5千円(以下) |
| 7割軽減 | 43万円+(10万円×(2人-1))=53万円(以下) |
くわしくは、「国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度」のページをご覧ください。
医療分の計算
|
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.08=41,600円 |
|---|---|---|
|
所得割 |
子 |
(50万-43万)×0.08=5,600円 |
|
均等割 |
3人 |
24,600円×3×0.8(注3)=59,040円 |
|
世帯割 |
1世帯 |
18,000円×0.8(注3)=14,400円 |
|
計 |
120,640円 |
|
後期高齢者支援分の計算
|
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.034=17,680円 |
|---|---|---|
|
所得割 |
子 |
(50万-43万)×0.034=2,380円 |
|
均等割 |
3人 |
10,600円×3×0.8(注3)=25,440円 |
|
世帯割 |
1世帯 |
7,300円×0.8(注3)=5,840円 |
|
計 |
51,340円 |
|
介護分の計算(40歳から64歳までの方のみ)
|
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.028=14,560円 |
|---|---|---|
|
均等割 |
2人 |
10,600円×2×0.8(注3)=16,960円 |
|
世帯割 |
1世帯 |
5,000円×0.8(注3)=4,000円 |
|
計 |
35,520円 |
|
(注3)「0.8」は、均等割及び世帯割の2割軽減のことです。
医療分と後期高齢者支援分と介護分を合計します。(各区分ごとに100円未満切捨てして合計)
120,600+51,300+35,500=207,400円
この金額が、この世帯の本年度分の保険税額になります。
年度途中から国保に加入したとき
年度末までの加入月数に応じて、月割りで計算します。
10月からの加入とすると、翌年3月までの6ヶ月間が本年度の加入月数になりますので、上記の世帯の例では、次のようになります(100円未満切捨て)。
- 医療保険分120,640×12分の6=60,320円
- 後期高齢者支援分51,340×12分の6=25,670円
- 介護保険分35,520×12分の6=17,760円
- 合計60,300+25,600+17,700=103,600円
年度途中の加入の場合、保険税額の通知と納付書は、市役所に加入の届出をされた翌月に送付します。
会社を退職したとき
会社を退職する場合、会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択することになります。くわしくは、「任意継続の保険料と国民健康保険税との比較」のページをご覧ください
年度途中で国保を喪失したとき
加入者ごとに、社会保険等への加入や転出などをされた(佐世保市の国保を喪失した)月の前月分までの加入月数に応じて、月割りで計算します。計算結果の通知と差額の納付書(還付が発生した場合は還付通知書となります)は、市役所へ国保喪失の届出をされた翌月に送付します。
計算方法は、2つ前の項目の「年度途中からの加入の場合」と同様になりますが、次の点にご注意ください。
- 次の項目の「国保税の納期」にありますように、国保税は1年間(12ヶ月)分を、6月から3月までの10回払い(1期~10期)となっております。
- したがって、各納期の税額は、その月分の国保税とはなりません。そのため、月割りで計算した結果、喪失の月以降にもお支払いいただく国保税額が残ることがあります。
介護分の課税について
- 世帯の国保加入者が年度途中で40歳になったときは、40歳到達の月から介護分がかかります。40歳到達の翌月から国保税が増額します。
- 世帯の国保加入者が年度途中で65歳になるときは、65歳到達の月以降の介護分はあらかじめ差し引いて計算しています。65歳到達後は介護保険料を別途お支払いいただきます。
75歳になるとき(後期高齢者医療保険との関係)
- 世帯の国保加入者が年度途中で75歳になるときは、75歳到達の月以降の国保税はあらかじめ差し引いて計算しています。75歳到達後は後期高齢者医療保険料を別途お支払いいただきます。
国保税の納期
国保税は、6月~3月までの10期に分けて支払います。
|
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
納期 |
|
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
6月以降に加入届をした場合は、残りの納期で分割して支払います。
例えば、10月に加入届をした場合は、11月(6期)から3月(10期)の5回払いとなります。
納期限についてくわしくは、「市税の納期一覧」のページをご覧ください。
年金から引かれる国保税について(特別徴収)
年金保険者(厚生労働大臣や共済組合等)が市町村に代わって国保税額を徴収することを特別徴収といいます。
年金が複数ある方の特別徴収対象年金は年金額によらず優先順位で定められています。
特別徴収は自分で納めに行く必要がなく、手続きもいらないのが利点です。ただし、特別徴収の対象となる年金や徴収額は任意に変更できません。
公的年金(障害年金や遺族年金を含む)を受けており、以下の条件のすべてを満たす世帯主は、年金から国保税が引かれます。(特別徴収といいます。)
- 世帯主が国保加入者であり、世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳であること。
- 介護保険料が特別徴収されていること。
- 介護保険料(年額)と国保税(年額)の合算額が特別徴収対象年金額の半額以下であること。
65歳の誕生日を迎えられた方へ
上記条件に該当する方は、概ね下の表にある時期から、特別徴収が始まります。
扶養する親族が国保税を負担しているなどの理由で、特別徴収されることを希望しない方は、「国民健康保険税の特別徴収から普通徴収への変更について」のページをご覧のうえ、手続きをしていただくようお願いします。
(めやす)
|
世帯主の方の65歳到達時期 |
特別徴収の開始時期(めやす) |
|---|---|
|
4月2日~10月1日 |
翌年度の4月 |
|
10月2日~12月1日 |
翌年度の6月 |
|
12月2日~2月1日 |
翌年度の8月 |
|
2月2日~4月1日 |
翌年度の10月 |
仮徴収と本徴収
年金の支給ごとの徴収額は、仮徴収、本徴収に分けて決められます。
毎年10月に徴収額が変更され、原則として12月から翌年度8月まで同じ額を徴収します。
ただし、本徴収額とのバランスをとる目的で、6月、8月の徴収額を変更することがあります。
|
4月 |
仮徴収 |
前年度の国保税を基に徴収します。継続的に年金から引かれている方は、前年度2月と同額が引かれます。仮徴収は額に変更がない限り事前に通知されません。 |
|---|---|---|
|
6月 |
||
|
8月 |
||
|
10月 |
本徴収 |
6月に決定した国保税の年額から、仮徴収額を引いた残りが、3回に分けて引かれます。新たに特別徴収が開始される場合は、年額の6分の1ずつ引かれます。 |
|
12月 |
||
|
2月 |
国保税額の変更などにより、特別徴収の中止、または普通徴収と一緒に徴収(併徴)となる場合があります。
【普通徴収から特別徴収に変更となる場合】
- 特別徴収の条件に該当する場合
【特別徴収から普通徴収に変更となる場合(特別徴収の中止)】
- 年度途中に被保険者の資格を喪失した場合、国保税額が減額された場合など
【特別徴収と普通徴収の両方で徴収される場合(併徴)】
- 年度途中に国保税額が増額された場合(増額分を普通徴収で納めます。)など
遡及賦課について(加入が遅れると国保加入すべき時までさかのぼって課税されます)
国保税は資格が発生した月、つまり社会保険資格を喪失したり、転入した月から課税されます。加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国保に入るべき時点(国保の資格が発生した月)までさかのぼって、最大3年度分課税されます。
国保への加入や喪失の届出は、ご自身で行う必要がありますので、十分ご注意ください。くわしくは、「国民健康保険の届出は事実の発生した日から14日以内に」のページをご覧ください。
国保税の減免について
災害など(火災や自然災害等の被害)により、どうしても国保税を納めることが困難な場合は、国保税の減免を受けられる場合があります。災害などに遭われた場合は、お早めにご相談ください。
国保税額についてくわしくは医療保険課へ
佐世保市の国民健康保険に加入した場合の国保税額の試算など、税額についてくわしいことは、医療保険課賦課係へお問い合わせください。
- 試算する際には、必要に応じて前年中の収入状況、家族構成、退職時期(加入日)などをお尋ねします。特に、2月・3月(年度末)や4月(年度初め)は、世帯主及び加入者の給与または公的年金の源泉徴収票、確定申告書の控えなど、前年中の所得がわかるものをご準備のうえ、ご相談ください。
- メールや電話でのお問い合わせについては、個人情報保護の観点から、お答えできない事項もありますので、あらかじめご了承ください。
関連情報
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください