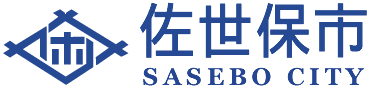ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
国民健康保険税Q&A
- (Q1)国保税は、誰が納めるのですか?
- (Q2)国保に加入すると、国保税はいくらくらいかかるのですか?
- (Q3)社会保険等の任意継続保険料と国保税ではどちらが安いですか?
- (Q4)会社を退職して収入が無いのに、国保税が高いのはどうしてですか?
- (Q5)職場の健康保険に加入したのに、国保税に関する通知が引き続き届くのはなぜですか?
- (Q6)月の初めに国保を喪失する手続きをしたのですが、その月の国保税は納めなくてよいですか?
- (Q7)職場の健康保険をやめてから何の保険にも入ってなかった場合は?
- (Q8)国保税を滞納するとどうなりますか?
- (Q9)コンビニエンスストアでも納付できますか?また、コンビニエンスストア納付は手数料がかかりますか?
- (Q10)低所得の世帯に対する国保税軽減制度について教えて下さい。
- (Q11)国保税を年金から天引きされています。天引きしないようにできますか?
(Q1)国保税は、誰が納めるのですか?
(A1)住民票上の世帯主に納めていただくことになります。
国保税は、世帯主に課税することが地方税法及び条例で定められています。
そのため、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入している場合でも、納税通知書は世帯主あてにお送りします。
この場合、税額計算では、実際に国保に加入している方の所得のみが、所得割の対象となっています。
(Q2)国保に加入すると、国保税はいくらくらいかかるのですか?
(A2)世帯主と加入者等の所得金額や、加入人数により、国保税額は異なります。
国保税の算定のための基本事項
- 世帯ごとに計算します。(一世帯分を世帯主の名前でまとめて納めることになります。)
- 年度(4月から翌年3月)単位で計算します。
- 佐世保市の国保税額を算定する要素は、所得割、均等割、世帯割の3つがあります。
- 医療分と後期高齢者支援分と介護分(40歳以上65歳未満の方のみ)をそれぞれ計算し、その合計額が国保税額になります。
- 課税すべき年度(4月から翌年3月)の、前の年(1月から12月)の所得を用いて、税額を計算します。
佐世保市の国保税の税率や計算方法については、こちらをご覧ください。⇒国民健康保険税額の算定
(Q3)社会保険等の任意継続保険料と国保税ではどちらが安いですか?
(A3)社会保険等の任意継続保険料と国保税の、算定の基になる金額や料率はそれぞれ違うため、一概にどちらが安いということは言えません。
どちらかを選択される場合は、事前に協会けんぽ等と市役所の両方にお問い合わせいただき、税額等を比較検討のうえ、手続きをお願いします。
関連事項については、こちらをご覧下さい。⇒任意継続の保険料と国民健康保険税との比較・国民健康保険税額の算定
(Q4)会社を退職して収入が無いのに国保税が高いのはどうしてですか?
(A4)加入時現在収入がない方でも、国民健康保険税は、地方税法等により、課税すべき年度分の前年中(1月から12月まで)の所得をもとに計算するので、前年中の所得が多いと国保税は高くなります。
国保税の支払いが難しい場合は、収納推進課へご相談ください。
(Q5)職場の健康保険に加入したのに、国保税に関する通知が引き続き届くのはなぜですか?
(A5)次のような事例が考えられますので、ご確認ください。
1同一世帯内に国保加入者が残っている場合
(Q1)にもありますが、国保税は、世帯主に課税することが地方税法及び条例で定められています。
つまり、同一世帯内に国保加入者が残っていれば、その方の分の国保税の通知書を世帯主宛てにお送りしています。
2国保の喪失届が出ていない場合
国保以外の健康保険に加入された場合には、国保の喪失届を出してください。
喪失届が出ていないと、国保加入の状態のままとなり、国保税が課税されます。
届出については、こちらをご覧ください。⇒国民健康保険の届出
(Q6)月の初めに国保を喪失する手続きをしたのですが、その月の国保税は納めなくてよいですか?
(A6)お納めいただくようお願いします。
国保税は1年分(4月から翌年3月の12ヶ月分)を、6月から3月までの10回払い(1期~10期)となっております。つまり、各納期の税額は、その月分の国保税とはなりません。よって、月割りで算定した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保税額が残ることがありますので、お納めいただくようお願いします。
国保税の算定のやり直しは、手続きをいただいた翌月に行いますので、お手続きいただいた翌月に更正決定通知書をお届けします。
なお、算定のやり直しによって、納めすぎが生じた場合、滞納がなければ還付させていただくようになります。
月割り算定等については、こちらをご覧下さい。⇒国民健康保険税額の算定
(Q7)職場の健康保険をやめてから、何の保険にも入っていなかった場合は?
(A7)国保税は国保資格を取得した月(前加入健康保険の有効期限の翌日)からさかのぼって課税されます。
そのため、加入の届出が遅れてしまった場合、届出をした月から課税されるのではなく、国保資格を取得した月までさかのぼって、最大で3年度分の国保税が課税されることになります。
(Q8)国保税を滞納するとどうなりますか?
(A8)国保税を滞納すると、保険証の有効期限が短くなる場合や、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となる場合があります。
また、特別な事情もなく国保税を滞納すると、税の公平を保つため、差押え等の滞納処分を行うことになりますので、収納推進課へ早めの納付相談をお願いします。
納付場所、督促手数料、延滞金などについては、こちらをご覧ください。⇒市税の納付について
(Q9)コンビニエンスストアでも納付できますか?また、コンビニエンスストア納付は手数料がかかりますか?
(A9)金融機関等に加えて、納付書裏面に記載されているコンビニエンスストアで納めることができます。手数料はかかりません。
納付書が納期毎に1枚ずつ切り離されているため、納付書の保管や、納付の際には税目や納期をよく確認して納め誤りをされないよう、ご注意ください。(納付の際は、納付書をご持参ください。)
バーコードが無い納付書は、コンビニエンスストアでは納められません。
(Q10)低所得の世帯に対する国保税軽減制度について教えてください。
(A10)軽減基準に該当する世帯については、軽減した後の金額で課税されます。(収入がない場合でも、所得の申告は必要です。)詳細は以下のリンクをご覧いただくか、医療保険課賦課係にお問合わせください。
軽減制度の詳細については、こちらをご覧下さい。⇒国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度
(Q11)国保税を年金から天引きされています。天引きしないようにできますか?
(A11)手続きをしていただくことによって、口座振替の納付方法に変更できます。(納付書による納付方法への変更はできません。)
手続き方法等の詳細については、こちらをご覧下さい。⇒国民健康保険税の特別徴収から普通徴収への変更について
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください