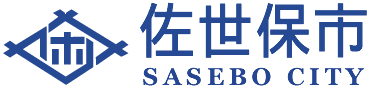ここから本文です。
更新日:2025年8月1日
国民健康保険出産育児一時金の支給申請
【1】対象者・支給額
(1)対象者
妊娠4ケ月(12週)を超える本市国民健康保険の被保険者(加入者)
(妊娠12週以上あれば、出産、死産にかかわらず支給対象となります。)
分娩者が社会保険等に1年以上加入後(社保扶養は含まない)、社会保険等を喪失して半年以内に出産された場合、原則、社会保険等から出産育児一時金は支給になります。
該当される被保険者は、喪失された社会保険等に連絡していただきますと「資格喪失等を証明する書類」が交付されますので、その書類を医療機関等に提示してください。
(2)支給額
50万円(※48万8千円)
令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(※40万8千円)
(※産科医療保障制度に加入されていない医療機関等で出産した場合の支給額)
【2】制度の概要
1.出産育児一時金の支給には次の2つの方法があります。
(1)医療機関等の窓口において、被保険者が出産費用を支払う負担を軽減するために医療保険者から医療機関等に直接支払う方法。(直接支払制度と言います。)
(2)医療機関等の窓口において、被保険者が出産費用を支払います。その後、被保険者が医療保険者へ申請し医療保険者から被保険者に支払う方法。
2.直接支払制度の合意文書について
上記(1)の場合、被保険者と医療機関等において、出産育児一時金の代理申請・支払いに係る直接支払制度を「利用する」旨を、上記(2)の場合「利用しない」旨を「合意文書」にて取り交わしていただきます。
合意文書は医療機関等に備えられており、被保険者用と医療機関等用の2部が作成され、1部が被保険者の退院時に医療機関等から渡されます。
【3】直接支払制度を利用した場合
1.出産育児一時金と出産費用の差額
医療機関等から出産費用の内訳を記した領収・明細書等の交付等があります。
(A)出産費用が50万円を超えた場合は、被保険者が医療機関等に差額分を支払ってください。
(本市に申請の必要はありません。)
(B)出産費用が50万円を下回った場合は、差額支給分を医療保険者(本市)に申請してください。
2.上記(B)の50万円を下回った差額支給申請の手続き方法
(1)申請方法
下記(ダウンロード)の「国民健康保険出産育児一時金申請書」に必要事項を記入して提出ください。
(2)申請先
市役所1階医療保険課1番窓口(給付係)または各支所、行政センターへ申請書を提出してください。(原則として郵送での提出は受け付けておりません)
(3)申請書を提出する期間
出産後2年以内となります。
(4)申請に必要な書類等
- 被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 世帯主名義の通帳(委任される場合はその関係書類等)
- 世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- (死産の場合は)医師の証明
- 医療機関等から渡された出産費用の内訳を記した領収・明細書等
(産科医療保障制度に加入している医療機関等で分娩した場合は、所定のスタンプが押してあります。) - 直接支払制度の合意文書(被保険者と医療機関等で取り交わした合意文書)
【4】直接支払制度を利用しなかった場合
申請方法・申請先・提出期間及び必要書類等については上記【3】2と同様です。
(直接支払制度の合意文書が『利用しない』になっており費用全額を支払った方が対象です。)
海外で出産をされた場合の手続き方法
申請方法、申請先及び提出期間については上記【3】2と同様です。
申請に必要な書類等
- 被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 出産された被保険者のパスポート
- 世帯主名義の通帳(委任される場合はその関係書類等)
- 世帯主のマイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 医療機関から受け取る出産費用の内訳を記した領収・明細書等
- 出生証明書
インターネットで申請
来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。
関連リンク先
- 支所・行政センター等(←ココをクリックしたら支所等の地図が表示されます)
- 産科医療保障制度(←ココをクリックしたら制度内容が表示されます)
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください